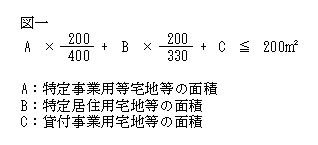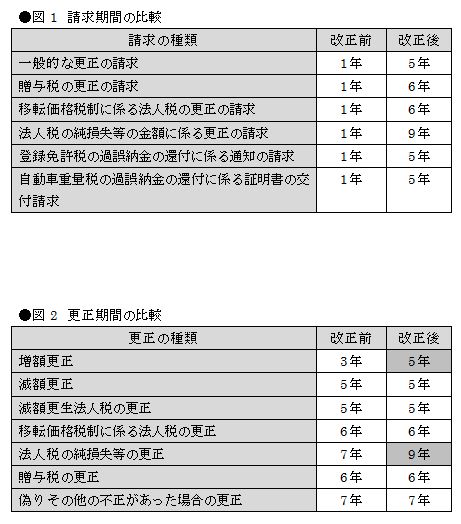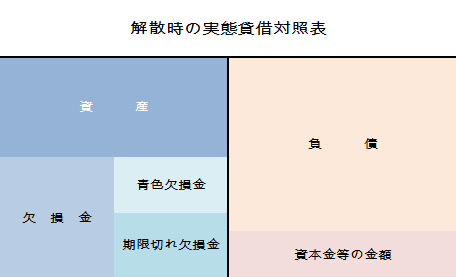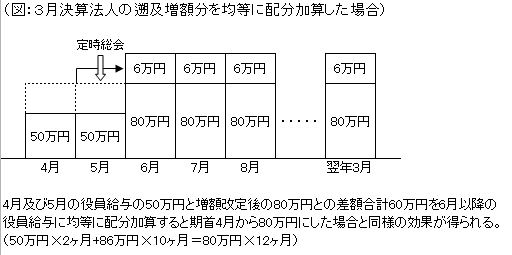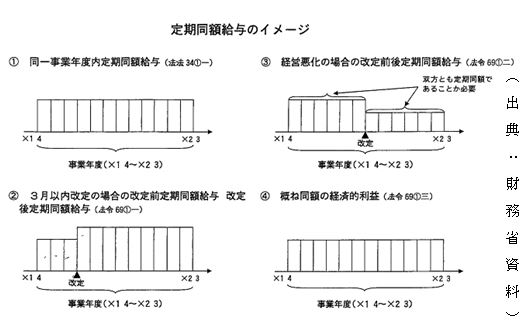これまでの実務において、長期の未完成請負工事等についての請負に係る収益及び費用の認識基準について、法人の選択により工事完成基準と工事進行基準のいずれかを選択適用することとされていた。 その結果、同様の請負工事契約に関して適用される収益の認識基準が企業の選択により異なってしまうという弊害(財務諸表間の比較可能性)があること、また我が国の会計基準を国際会計基準にコンバ−ジェンスしていく必要があることから、平成19年12月27日に「工事契約に関する会計基準」が公表され、今後は一定の要件「成果の確実性」が認められる工事契約及び受注制作のソフトウェアについては、工事進行基準を適用しなければならず、工事完成基準の適用は認められなくなる。
一、工事契約に関する会計基準の概要
ソフトウェアの受注制作においては、従来請負契約として工事完成基準(収益及び原価は完了、検収時に計上)を採用していた法人が多数を占めていた。 公表された本会計基準の適用範囲には請負契約のうち土木、建設
、造船や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容について顧客の指図に基づいて行う「工事契約」と「受注制作のソフトウェア」が含まれており、「成果の確実性」が認められる工事については工事進行基準(決算日に、収益及び原価をプロジェクトの進捗度に応じて計上)を適用することとされている。 従って、今後は工事進行基準を適用するケースが増加するものと予想される。
工事進行基準を適用するには、工事契約に係る認識の単位ごとに工事契約において当事者間で合意された「実質的な取引単位に基づく」こととされ、その進捗部分について「成果の確実性」が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用するとしている(会計基準8,9 )。 この成果の確実性が認められるためには、次の3要素を信頼性をもって見積ることができなければならないとしている。 ①工事収益総額 ②工事原価総額 ③決算日における工事進捗度
二、工事進行基準における税務上の取扱い
平成20年度税制改正において会計基準による会計処理との整合性を図るために、法人税法の改正が行われた。
改正のポイントは、次のとおりである。
法人が長期大規模工事(製造及びソフトウェアの開発を含む。)の請負をしたときは、所得の金額の計算上、収益の額及び費用の額のうち、政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金及び損金の額に算入する(法法64①)。 このため、会計上成果の確実性の判断のもと、工事進行基準又は工事完成基準のいずれを採用したかに係わらず、一定規模のプロジェクトについては、工事進行基準を適用することが必要となる(強制工事進行基準)。 一方、長期大規模工事以外の工事について、法人が政令で定める工事進行基準で会計処理した場合には、その経理した収益及び費用の額を所得の計算上、益金及び損金の額に算入することができる(法法64②)とされており(選択工事進行基準)、税務上も同様の処理を行うことが可能となっている。 原則として、平成21年4月1日以後開始する事業年度において着手する工事(受注制作)から適用されるが、経過措置として同日前に開始した事業年度に着手した工事についても先行適用ができることとされている。
① 工事進行基準の対象に、ソフトウェアの受注制作を加える(法法64①、法令129①)。
② 工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲について、工事期間要件を2年以上から1年以上に、請負金額要件を50億円以上から10億円以上にそれぞれ改正。
③ 請負の対価の額の2分の1以上がその工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われるものでないこと。
④ 工事進行基準を適用できる長期大規模工事以外の工事の範囲に、損失が生じると見込まれる工事(工事損失引当金)を追加。
⑤ 工事進行基準の適用により計上した未収入金は、金銭債権として貸倒引当金を設定できる。
活用のポイント
法人税法では、企業の恣意性の介入を排除するため、原則として費用の見越計上を認めていないので、ソフトウェアの工事契約(受注制作)から損失が見込まれる場合に、工事損失引当金として会計処理した金額については当該事業年度において損金の額に算入されないことに留意する(法基通2−4−19)。 また、工事進行基準を適用している工事に係る未収入金について、従来は目的物の引渡し前の未収入金は貸倒引当金の対象から除かれていたが、このたびの改正で、金銭債権として貸倒引当金の設定対象となることが認められたことにより、20年4月1日以後に開始する事業年度から貸倒引当金の対象となることに留意することも肝要である。 |